|
三条藩がなくなってから26年間、三条町と周辺の村々は出雲崎代官所の支配を受けてきましたが、慶安2年(1649)に村上藩領となりました。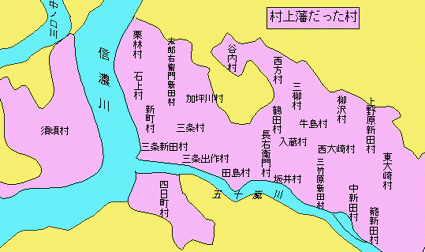
どうして三条が越後(今の新潟県)のもっとも北の村上藩の領地になったのでしょうか。村上藩は江戸時代はじめは村上周防守頼勝という人が藩主でした。その後、堀丹後守直奇が藩主となり、その子の時代にあとつぎがないことから一時幕府領となり、正保元年(1644)には、遠江国掛川(今の静岡県掛川市)から本多能登守忠義が村上藩主として着任しました。
しかし、5年後、本多忠義は奥州白河藩(今の福島県白河市)へ国がえとなり、そのあとへ播州姫路(今の兵庫県姫路市)の松平藤松が村上藩主となりました。松平藤松の父は、徳川家康の孫にあたり、名を直基といい、姫路城の主でした。姫路城は、中国、四国、九州に多い外様大名(徳川家の家臣でなかった大名)を監視する重要な場所にあります。ところが、父直基は藤松がわずか7さいの時に急死したため、藤松は幼くしてあとをついだのですが、7さいの姫路城主では、外様大名へのにらみがきかないとみられ、姫路から村上のほうへ国がえとなったと考えられます。
ただし、村上藩はそれまで10万石の領地だったのですが、あらたに旧三条藩領がつけ加えられ、姫路藩と同じ15万石に格付けされました。また、藤松という幼名も松平大和守直矩と改め、慶安2年から寛文7年(1667)までの18年間、村上藩主として、三条をふくむ15万石の領地を支配しました。(平成9年12月)
|