|
元和2年(1616)、三条藩の領主となった市橋長勝は、三条城の建て替えを主だった家来と相談しました。それまでの三条城は「三条島の城」と言われ、戦国時代から須頃島の先端(今の三条競馬場付近と言われている)近くにあって、信濃川が大水になると、城の周辺まで水びたしになる状態でした。また戦国時代はたびたび戦いがあり、城の堀や囲いなどが大変いたんでいました。そのため城を別の場所へ移し、新しい三条城を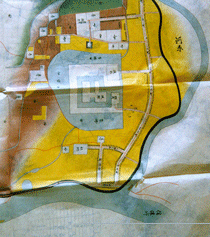 建造することになりました。 建造することになりました。
新しい城を作るためには徳川幕府の許しを得なければなりません。新城建造の計画を報告すると、幕府月番老中(今の内閣官房長官のような役職)から、「三条城は会津街道(今の新潟県と福島県を結ぶ道路)を監視する重要な城であるから、しっかりとした城にするように」といった意味の指示があったということです。しかしそれだけでなく、今までの三条城は高田(今の上越市)の出先の城であったけれども、今度は小さいながらも独立した三条藩の城として、りっぱな城が求められたわけです。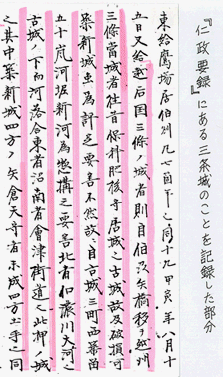
そこで新しい三条城は、古い城から3町(約330メートル)ほどへだてた所の、今の元町(旧古城町付近)へ建造されることになりました。その時代の五十嵐川は今の三竹辺りで流れが二つに分かれていました。新しい城は五十嵐川の流れを城の構えに生かして築造したと言われています。市橋家のことを書いた『仁政要録』には「五十嵐川という大河を築き留め、新川を堀り、城のすべての堀に水を引き入れ、城の構えを要害とした」という意味の記録が残っています。(平成9年4月)
|