|
およそ400年前、日本の最もえらい武士となった豊臣秀吉は、全国からできるだけ多くの年貢(今の税金)をとりたてるために、検地という田畑などの調査を行ったことは前に話しました。では、そのころ、田畑などの土地の面積は、どんな単位で計算されていたのかについて、説明しましょう。
田畑は、今はメートル法といって、平方メートルという単位で、広さをあらわします。1平方メートルというのは、たてと横が1メートルの正方形と同じ面積のことですね。いま農家の人たちは1アール、10アールというように、田畑の広さを言いますが、1アールは10メートル×10メートルの広さのことです。では、400年前はどうだったでしょうか。
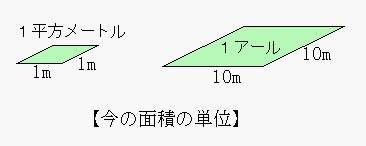
昔は田畑を1歩、2歩という単位で計算していました。1歩は宅地や家屋などの面積の単位であった1坪と同じです。1坪は家屋の柱と柱の間を1間とか2間と言いますが、1間×1間が1坪(または1歩)で、1間という長さは6尺(1・81メートル)のことです。田畑は、30歩を1畝歩としました。なぜかというと1か月は30日ですので、1畝歩は1か月に食べる米の収かく量に関係があったと言われています。
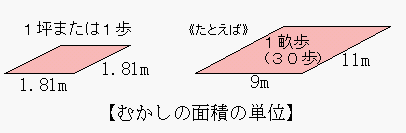
1畝歩を10倍したのが1反歩です。1年は12ケ月ですから、本当は12倍しなければなりませんね。豊臣秀吉が検地をする前は、たしかに360歩が1反歩だったのです。それを300歩を1反歩にして年貢の量を360歩と同じにした、と言われています。そうすると、余計に年貢をとることができるわけです。(平成8年9月)
|