|
今まで大崎地区や本成寺地区の山にいくつかの山城があったことを話しましたが、では現在の三条市の中心部である平野部にはどんな山城や館があったのでしょうか。今の東裏館、西裏館辺りを江戸時代は裏館村と言っていました。
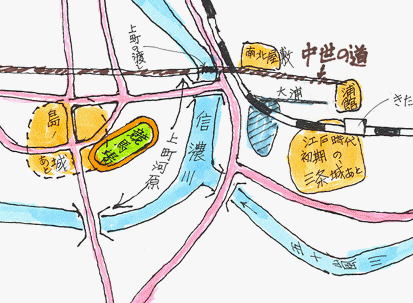
また三条の町の今の三条小学校の近くに江戸時代のはじめころに三条城がありました。そのことから、三条町の裏にあたる所に館があったので、裏館と言うようになった、と言われています。しかし、もっと古い時代に今の三条市街地辺りより裏館の方が早く発てんしていたことが分かり、三条町の裏だから裏館というわけではない、と考えられるようになり、「浦の館」があったことから「うらだて」とよばれるようになった、という説が有力になってきました。
浦というのは、海や湖などがわん曲して陸地に入りこんだ所という意味です。今から400年から500年前の三条周辺の信濃川や五十嵐川は、今よりずっと川はばが広く、今の第一産業道路(国道289号線)辺りから裏館小学校近くまでの一帯が水であふれ、湖のようになっていて、その岸の辺りに館があり、それが、浦の館であったのではないかと言われています。
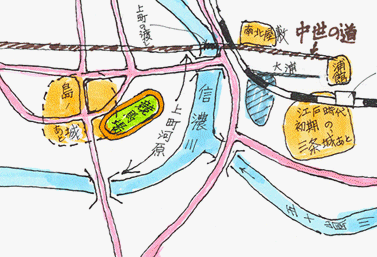
昔は舟の交通が中心で、浦というのは重要な場所だったのです。次に三条島の城ですが、三条小学校辺りに城が築かれる前に、今の競馬場の辺りに城があったのではないかと言われていました。しかし、くわしく調べると、そこに城があったという証こはなく、別の場所だったのではないか、という疑問がありますが、はっきり分かりません。(平成7年8月)
|