|
平安時代、鎌倉・室町時代に、地方を領有支配するものとして荘園や保がありました。荘園は庄園とも書き表すこともあります。
三条周辺ではどのような荘園があったかといいますと、現在の市の中心部から井栗地区辺りにかけては大槻荘があり、本成寺地区から栄町辺りが大面荘、加茂市を中心にして三条市の一部をふくむ地いきが青海荘であったと言われています。また、それらの荘園より古い時代に槐田荘も三条市いきのどこかにあったと考えられています。
では、このような荘園はどういうものだったのでしょうか。荘園が発生する前の奈良時代、今から約1300年前ころは、公地公民と言って、すべての土地は国家が所有するもので、そこに働き生活する人たちは公民である、という考え方が国の政治の基本となっていました。しかし、時代の移り変わりとともに、荒地の開こんが進められました。そこで、力のある神社や寺、貴族や地方豪族たちが大勢の人を動かして土地を開こんし、やがてそれらの土地が有力者の私領となり、荘園になりました。
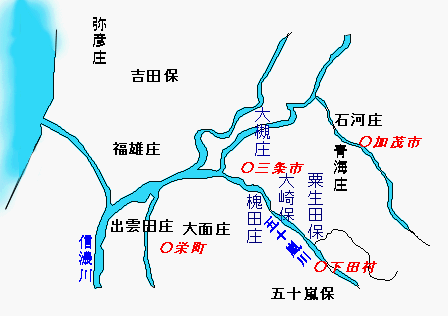
荘とは、もともと身分の高い貴族たちが地方に持っていた別宅を言い、別宅の周囲の土地もふくめて荘とよんでいました。いまでも、金持ちが持つ別宅や屋しきを別荘と言いますね。保というのはどういうことかといいますと、荘園は大きな社寺や貴族、地方豪族の私領であったのに対し、保は国衙領ともいう国が直接支配する領地と言ってよいでしょう。
三条周辺では、大崎保(現在の大崎地区)や粟生田の保がありました。これら荘園と保について、次でもう少しくわしく説明します。(平成6年4月)
|